結論から言えば、境界標が無くても土地を売ることはできます。ただ、手続きと責任の違いなどについて正確に理解している人は実は少ないので、注意しましょう。
境界を明示する理由
不動産売買契約では、地番などの登記記録の内容を記載して売買対象となる土地を特定します。
しかし、実際の土地には線などが描かれているわけではありませんから、どこからどこまでが売買の対象の土地なのか、契約書の記載だけでは分かりません。そこで、現地の境界標を確認することで、売買対象の土地を特定します。
そのため、原則として、土地の売買を行う場合には、売主は買主に対して、境界の明示をする義務を負います。
境界標と境界線
通常、土地の角にあたる部分には境界標というものが設置されています。
境界標には色々な種類があり、コンクリート製の杭や、金属製のプレート、金属の鋲などが代表的なものです。ほかに、古いものでは大理石などの石、塀などに設けた刻み目(キザミ)などがあります。
 コンクリート杭
コンクリート杭
 金属プレート
金属プレート
 金属鋲
金属鋲
 大理石
大理石
この境界標をもとに土地の範囲、形状を明確にするわけです。境界標と境界標を結んだ線が境界線となります。
明示は、土地の角にあたる部分に設置されている境界標を指し示して行います。
境界標が見つからない場合
境界標は、地面やコンクリート舗装、塀の下などに埋まっていることも多く、もとから全部の境界標が確認できる物件はあまり多くありません。
この場合、まずは境界標があると思われるところを掘り返すなどして、境界標を探すことになります。
草や土などに隠れている程度であれば、不動産会社の担当者が探してくれることもあります。
おそらく建物建築時に土を盛ったためと思いますが、僕自身、スコップで地面を数十センチ掘って、なんとか境界標を探し当てた、という経験があります。
しかし、塀やコンクリート舗装などの構造物の下にあると思われる場合、それらを砕いて境界標を探すのは、普通の人間には難しいので、専門家である土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。
 塀の下の境界標
塀の下の境界標
測量(境界標の探索・敷地の計測・隣地所有者との境界確認)を行うと数十万円以上かかりますが、境界標の探索だけであれば、数万円でやってくれる土地家屋調査士もいます。
境界標が無い場合の対応策
ところが、専門家に探してもらっても結局見つからない、ということもあります。
古くに設置された境界標では、いつの間にか紛失してしまっていたり、そもそも設置されていなかった、ということが考えられます。
境界標が無い場合、以下のいずれかの方法をとります。
① 新しく境界標を設置する。
② 境界に関する説明書で代用する。
③ 既存の測量図で代用する。
④ 買主に非明示を容認してもらう。
どの方法を採用するべきなのかは、物件の状態や価格、売買スケジュールなどによって異なります。
なお、公道(国や地方公共団体が所有・管理する道路)、私道(国や地方公共団体以外が所有・管理する道路)との境界については、境界標の設置を省略できる、とする場合もあります。
① 新しく境界標を設置する
境界標は、隣地との境目を示す目印のため、片方の土地の所有者の独断で設置することはできません。つまり、境界標を設置するには、隣の土地の所有者の承諾が必要となります。
境界標が移動や紛失した場合に備え、復元できるように、座標を測定して設置するので、土地の計測作業も必要です。要するに、測量を行うことになるため、数十万円の費用がかかります。
将来的なトラブルを避けるという点では、最も優れている方法ですが、以下のような問題があります。
・ コストが高い
・ 隣地所有者の協力が必要
・ 時間がかかる
② 境界に関する説明書で代用する
境界標は無いけれども、この塀の角のはず、というように境界位置を説明可能な場合には、境界に関する説明書「境界説明書」で代用する、ということもできます。
これは、売主が、「境界はここですよ」と書面にして買主に知らせる書面です。境界標と異なり、両者の合意が前提になっていないため、売主と隣地所有者で主張が異なってしまう可能性があるので、慎重に確認して作成する必要があります。
③ 既存の測量図で代用する
境界標そのものは無いけれども、古い地積測量図など過去の測量図がある、という場合には、その測量図により境界を明示する、という方法を取ることもあります。
法務局に備え付けられている地積測量図には、昭和30年代のものなど、かなり古いものもあるので、その場合は、現地状況との照合を行っておくことが望ましいでしょう。 また、遠方の物件などで、明示を行うことが難しい場合には、非明示だが測量図は交付する、という形を取ることもあります。
④ 買主に境界の非明示を容認してもらう
前述の①~③は、境界を明示する方法として、新規に境界標を設置する、または境界標を設置はしないが説明書または測量図で説明する、というものでした。
売主が、物件について何も知らず、地積測量図など古い図面も存在していない場合などには、境界を明示しない、いわゆる境界非明示とする場合もあります。
境界非明示と契約不適合責任免責の違い
このように境界の位置を明示しない、つまり境界非明示でも、土地を売ることは可能です。
ただし、境界非明示とした場合でも、境界についての契約不適合責任(欠陥についての責任)がない訳ではありません。
この点は不動産業者でも正確に理解できている人は少なく、「境界非明示」と後述する「境界についての契約不適合責任免責」を混同している人も多いので注意が必要です。
境界非明示でも、買い手が購入するにあたっては、境界について一定の認識があると考えるのが自然です。境界の明示は、境界についての認識を売主・買主でそろえる手続きですから、それを行わない境界非明示の場合には、境界についての認識が売主・買主間でズレやすくなります。
結果として、売主にとっては訴訟等のリスクが高くなる可能性がありますから、安易に非明示とはしない方が良いでしょう。
境界についての契約不適合責任免責
契約不適合責任は、任意規定と呼ばれるもので、当事者同士が合意すれば、「免責」つまり「責任を負わない」とすることができます。
契約不適合責任免責の特約は、不動産の売買契約では一般的なもので、古い建物の売買など、その品質の保証が難しいと思われる場合によく利用されおり、境界においても、この特約を設定することが可能です。
ただし、境界は、土地においては最も基本的な要素ですから、その全部を免責にしようとすると、買主側のリスクが大きくなり、かなりの価値低下が生じます。
また、曖昧な設定にすると、売主が免責の対象と考えても、買主はそのように認識しておらず、訴訟に発展する、ということも考えられます。
この辺りは、不動産会社の担当者によって、かなり結果に差がつく可能性がありますので、経験・実力のある人に相談するのが良いでしょう。
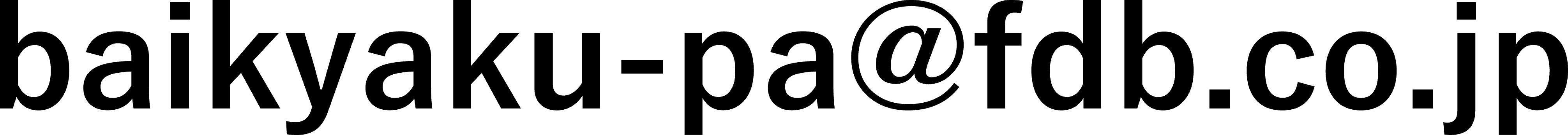 へご連絡下さい。
へご連絡下さい。